※ソースに動画あり発掘調査が続く吉野ヶ里遺跡のいわゆる「謎のエリア」で、国内で最古級とみられる銅剣や、銅矛を作る際に使われたとされる鋳型などが新たに発見されました。
吉野ヶ里遺跡の北側の「謎のエリア」で去年12月に新たに見つかったのは、国内で最古級とみられる弥生時代中期の鋳型2点です。
見つかった鋳型のうち1点は、両面が銅剣や銅矛を作る際に使われていたと推定されています。
朝鮮半島の石材に類似する角閃石岩で、角閃石岩が吉野ヶ里遺跡から出土したのは初めて、県内では小城市の土生遺跡に続き2例目だということです。
一方、もう1点は去年9月に出土した鋳型と同じ個体のもので、今回は銅剣や銅矛の刃の部分だということです。
2点は去年4月に発見された石棺墓から、南西10メートルほど離れた場所で見つかったということですが、
時期などから見て弥生時代後期のものとみられる石棺墓との直接的な関係はないということです。
県は15日から吉野ヶ里遺跡展示室で今回発見された出土品を展示し、35年前に「吉野ヶ里フィーバー」が巻き起こった2月23日には講演会も予定しているということです。
関連スレ
【考古学】古代の戦闘民族スキタイ人は人の皮で矢筒を作っていた ヘロドトスの『歴史』の記述に初の証拠 “伝説”の正しさを証明 [ごまカンパチ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1707923543/
ふむ(´・ω・`)
武器は権力の象徴にもなるけど恐らくは軍隊がいたんだろうな
そうなると時代的に覇権国家があったんやろ
吉野が里には見張り台や防柵があったらしいから戦があったのは間違いないと思う
魅力的な農作物や海産物
戦はやはりあっただろうね(´・ω・`)
神社が建っていてそこだけ発掘出来なかったエリアだったから。
神社が移転してやっと発掘出来るようになったら
石棺やらなんやら出てきた
古代の人がそこが神聖な場所だから神社を建てたということか?
神社が建ったのは江戸時代後期らしい
ただその辺りで一段高くなっている一等地的な場所だから
弥生時代でもそのエリアは上級国民が占有していたんじゃなかろうか
その後、魏が帯方郡を手中に収めたことによって魏とも交易可能になったんだよな
邪馬台国かどうかは知らんけど
2~3世紀の鉄の鏃が大量に出土してんだよな
九州を南北に分けるかのように
九州南部は呉と交流があり大量の武器が出回っていた
そして北部九州は魏と交流できるようになり、九州で魏呉の代理戦争をやってたんだろなーと想像してる
せめて、はがねのつるぎからいこうや。
簡単にはがねなんて言うが当時からすれば
あれ凄いテクノロジーなんだよな
ので話題にする必要は無い、当時の本州はすでに
鉄剣が使われていた。九州は時代遅れ
鉄剣
てっけん
鉄製の剣。日本では石剣、銅剣にかわって、弥生(やよい)時代中期中ごろに出現する。
現在、弥生時代に属する鉄剣は北部九州を中心にして60例ほど出土している。技術の発展過程を考えると
まず加工しやすい銅が先に普及し
次に鉄の時代が来る
本土に銅がないということは銅の時代に文化がなく、鉄の時代になってから初めて北九州から輸入、又は導入されたということになる。
墓にしても何をもってして卑弥呼の墓だと断定するのだろうね
邪馬台国は滅んだと言われてるけど、移住した先に墓を作り直した可能性はあるのかね?
どういう滅び方をしたのか知らんけど、墓荒らしとかいなかったのかね?
出土品が大量に出たからってのはどこまで根拠になるのかね?
数十年から数百年の誤差がある考古学で本当に邪馬台国なんてものを断定できるのかね?
親魏倭王印がでりゃ議論の余地ないだろ
卑弥呼(の外交官僚)は文字を使ってたから金石文が出ることも絶無じゃない
未発見の遺跡に眠ってる可能性はあんまりないだろうが
魏志倭人伝の原本、またはより古い写本が発見されたら終わるかもね
墓を必ず傍に作る
奪われた物ではないこの辺を証明するのが無理じゃね
>>43
今更見つからんのでは?
出土物が他所から持ち込まれたものだという証明はそう考える奴が自分でやるべきこと
吉野ケ里の埋葬者が現地人だというのをいちいち証明する必要がないのと同じ
ある通りに進むと、有明海になると言う説がある。
そういう意味では、吉野ケ里遺跡は、邪馬台国に
非常に近い。文献論的には、大和ではなくて、
山門(やまと)という地名が、福岡市西区の
姪浜に近いところにあるので、そこがヤマト
であるという、九州説を強く支持する物証
(地名)がある。

https://i.imgur.com/EmXw7Sk.png
纒向遺跡に対する日本の炭素14年代測定及び年輪年代測定は、なぜか国際基準よりも100年古い結果がでる。
例えば建立と再建が資料によって明確な法隆寺に当てはめると【上宮聖徳法王帝説により推古15年(607年)頃建立・日本書紀により1度焼失し670年に再建】という高校生でも知っている事実に対して、500年代中期という結果が出る代物…
つまり纒向遺跡は卑弥呼の没後100年以降の物という事。これは日本の考古学会により、危険な【捏造】が行われている証左であろう。
纒向の遺跡と類似の祭祀跡が滋賀県の伊勢遺跡で発掘され。伊勢遺跡の方が纒向より古い。近江には最大級の鉄器工房と大規模な水田跡もでて来ており中国から輸入した剣も出てきたりと卑弥呼直前は国内の最大勢力であったことがほぼ疑いない状況。この勢力が奈良に勢力を拡大し新都として作ったのが纒向ではないのか?との研究が急速に進んでいる。
東瀬戸内海の勢力が大和を支配で問題ないんじゃないの?
最初期は各地豪族共立だったと思うが
世代重ねると直ぐに土着豪族化してて
東瀬戸内海からの影響はなくなる
継体もそうだったし違和感はない
「卑」弥呼 こんな当て字で記述される国や人がいた事が それほどうれしいか?
差別が恥ずかしいのはされてる側じゃなくてしてる側だよ
スサノウを祀る櫛田神社があり、
大蛇退治の伝説も言い伝えられている。
コレが紀元前3世紀から言い伝えられていたのだから驚きだ。
近年の銅鐸及び銅剣の出土によって決定した訳だが、
実際にその隣にスサノウ伝承が残っている、
櫛田宮がある事が日本の歴史の素晴らしい所だな。
の石だった事が判明しているので普賢岳付近の
海岸から巨大ないかだに乗せて吉野ケ里付近の
海岸まで運んだと言う事だ
この前騒いでて何も出なかった石棺の蓋は多良岳の産だったらしいすよ
ちょっと怪しい神社ではあって、ググってみるといろいろと面白い。全国の著名な櫛田神社のうち、もっとも古いのは三重県松坂市にある
神社で、二番目がこの佐賀県神埼市、三番目が富山県射水市、その後に
福岡県福岡市の櫛田神社、ということになるみたい。
で、松坂市の櫛田神社の祭神は大若子命で、大若子命と倭姫命が
話している内に倭姫命の櫛が落ちたのでその地を「櫛田」と名付けた
という由来があって、クシナダヒメとは関係ない感じなんだよね。
その後、景行天皇が佐賀に来た時にこの佐賀県神埼市の櫛田神社が
できたらしいのだけど、そこでも実は「神埼」の由緒になったくらい
の話しかなくて、スサノオもクシナダヒメもいきなり出てきた感じが
するんだよね。
まあ上でも書いたけど、そもそも「倭姫命世紀」が後世に書かれた
少し怪しい書物だし、さらに景行天皇やヤマトタケル、武内宿禰も
実在も怪しい人たちなもんで、解釈するのも難しいんだけどね。
引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1707923886/
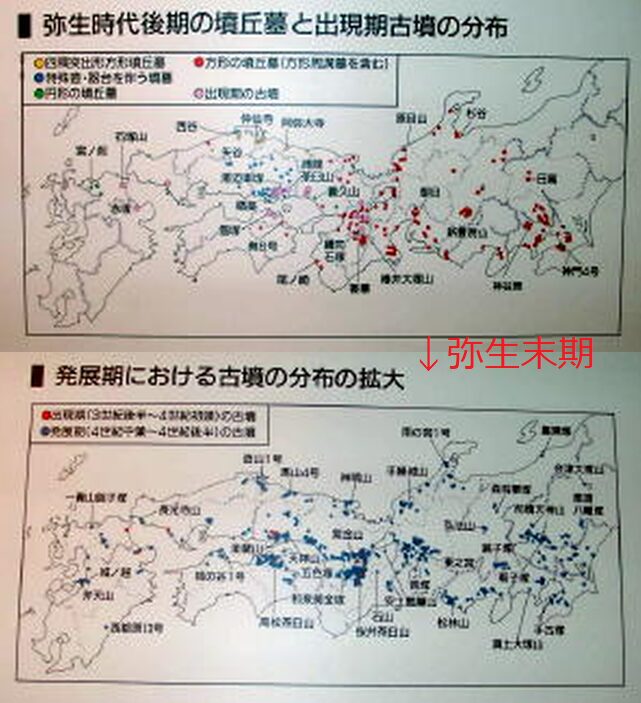
コメント