ここ最近の「教養ブーム」の影響なのか、歴史をテーマとした書籍に面白いものが随分と増えた。
その中でも良書と思ったのは、『古代ローマ ごくふつうの50人の歴史 ―無名の人々の暮らしの物語』(河島思朗著・さくら舎)だ。
これまで、古代ローマの歴史を扱った書籍は、カエサルやキケロといった著名な政治家や思想家を主役にしたものが多かった。一方こちらは、市井の名もなき人々。著作も評伝もない彼らの生活・人生を、西洋古典学者が、碑文といったわずかな手がかりから掘り起こし、興味深い1冊に仕上げている。
解放奴隷が経営したポンペイ随一のクリーニング店
本書では、ローマ建国史の概略を述べたのちに、クリーニング屋の店主がまず紹介されている。彼の名は、ルキウス・アウトロニウス・ステパヌス。男性の正装のトガは、「長さ五メートル、幅二・五メートル」もある毛織物で、自分で洗うのは大変。そこで彼のような専門業者の出番となる。
ステパヌスは、ポンペイでも指折りのクリーニング店で、複数の従業員を雇って仕事をした。作業工程は次のように描写されている。
<まず、衣服を洗剤で洗う。大きなたらいに液体をためて衣服を入れ、足で踏みつけたり、こすったりして汚れを落とす。洗剤にはカルシウムを含む土やアンモニア(発酵させた尿)が使われた。(中略)その後、きれいな水で洗剤を洗い流し、しっかりとすすぐ。洗濯屋では水を効率よく回すために、固定された大きな洗濯槽を設置していた。注水と排水の設備もあり、入り組んだ構造をしていた。(本書78pより)>
仕上げに乾燥、ブラッシング、磨き上げまであり、なかなかきつい労働だとうかがえる。作業にはステパヌスの奴隷も携わった。実は、店主のステパヌス自身が、妻ともどもかつては奴隷であった。それが主人に解放され、自主独立の道を歩んだのである。
ちなみに、古代ローマの市民社会では、種々の労働は忌避され、それは奴隷や元奴隷が従事するものとされていた。そのため、本書に登場する仕事人の多くが解放奴隷であった。
力なき帝国主義制度は大日本帝国の末路をみるとわかりやすい。
最後には世襲が全てを腐らせて滅亡するから持続しない。
ローマ史で言うと、貴族出身者が回してた時は比較的上手くいっていて、
出自が良くない親衛隊長とかが皇帝暗○して自分が成り上がるみたいなのを繰り返してた時は酷い結果になりがちだったけどなw
仮にローマ帝国がまだ続いていたら、その生活様式が続いてしまう。
何か新しい文化が生まれるにしても、それは旧来の文化と衝突しない事が求められるだからそうであったならつまり人類の歴史はむしろ1000年くらい遅れていただろうという事
モンゴルでなくてか?
正確には、ビザンツ帝国=東ローマ帝国の後継者気取りウクライナ侵略も、思想的動機はそれ
よし!ならば十字軍を派遣しよう!コンスタンツノープル占領だ!
キリスト教で白人の文明進化が遅れたのは事実だろな
けど結局鉄砲技術を進化させたのは白人でそれが現代の白人の人口比率の
多さと地球上の資源占有率に繋がっている
剣までの時代だと人種間の差はあまりなかったからなw
陸地が全部草原ならなw
ジャングルのベトナムに侵攻できなかったし
海で囲まれた日本にも侵攻できなかった
地続きの平坦な陸地しか侵攻できないのが遊牧民族w
遊牧民族の習俗を捨て去らない限りそれがモンゴルの限界だろwww
無理だ。チンギス・ハーンの子孫達は呪われ過ぎてる。しかも呪いをかけたのはチンギス・ハーン本人というね。
まあチンギス・ハーン自身に言わせれば「せやかて避けられへんやんか。他にどないせいっちゅうねん」ってトコロだろうが。
オカルトチックで抽象的な表現になるが、チンギス・ハーンとモンゴル帝国の歴史に詳しい奴なら判って貰えるハズ。
キリスト教会のネットワークは金融機関として優れていたからな
現代でもヴァチカンの基幹産業はマネーロンダリングだ
産業の勃興にはプロテスタントの台頭が必要だが
ヴァチカンの腐敗は必然なので
プロテスタントの誕生もまた必然なんだと思うよ
アレクサンドリアで蒸気を使った実験やからくりの開発やってたって
何かで見たことがある
あの頃って重力とか浮力の概念って思考実験で
なんとかしてただけで、アリストテレスの
万物は元あった場所に還ろうとする、が有力で
火は太陽の元へ還ろうとするから上に立ち上る的な
場当たり的なもんだから、ちっと難しい気もする
古代ローマって建築や法学や統治システムは特筆すべき文明だったと思うけど
数学や自然科学的アプローチは古代ギリシアからあんま変化なく経済システムも原始的な貨幣経済の域を脱していなかったから
仮に帝国が生き延びたとしても極めて早期の産業革命は難しかったんじゃないかなあ
ガリレオ家の長男って意味でガリレオの中のガリレオって感じでガリレオって呼ばれる。
ガリレイはガリレオの複数形。
フィボナッチなんて名前ですらなくあだ名やで
東ローマ帝国がオスマン・トルコに滅ぼされると、ロシアが第三のローマ名乗ったり、
ファシスト党のムッソリーニがローマ帝国復活目指したり、
まさに全ての道はローマに通ず
イスタンブルをコンスタティノープルを改名して首都にすればと妄想してみる
敢えてローマ近辺ではなくビザンツ周辺がローマ帝国を名乗った方がロマンを感じるのは俺だけか
キプロス島ですら、トルコ系とギリシャ系で分断されてる
イスラム教とキリスト教の対立は根深いから合併は無理
トルコはEUにも今だに入れてもらえない
ギリシャとトルコの合併があり得ないのは知っているが
地理的には全然ローマじゃない所にあるのにローマ帝国と名乗る国が1453年まで存続したことにロマンを感じるのさ
歴史的には正当なローマ帝国(東半分)だし
各地の軍事集団が軍閥化して統制から外れるのは中国はおろかアッシリア、古代エジプトの頃から繰り返されていたことだししょうがないな
それだけでなく、カラカラ帝のアントニヌス勅令とゲルマン人流入が悪い方に作用しあって、兵力の根本がが弱体化し続けた上に、
他の要素も重なって、にっちもさっちもいかない状態になっていた
西ローマ帝国に流入してきたゲルマン民族とかいう蛮族にローマ文化と文明人としての生き方を教えたのはキリスト教なので逆なんだよなぁ
そういう意味で言ってるのかもしれないが
問題は、ローマ文明を引き継ぐ受け皿無しに崩壊したせいで知識が遺失した事で
モンゴル軍がバクダッドのアッバース朝滅ぼしてから、アラブ人のイスラム帝国はダメになった
モンゴル軍は文明の荒廃もたらした
神聖ローマ潰したらそっから統一ドイツ国家なんてのが現れてフランスに牙剥いてきたんだからやぶ蛇もいいとこ
ローマ帝国は4世紀に東と西にそれぞれ1人ずつの皇帝、副帝に権力を継承させる形で分裂し、西ローマ帝国と東ローマ帝国に分かれた。
その後西ローマ帝国は5世紀に滅亡。
東ローマ帝国は15世紀に滅亡。神聖ローマ帝国はそのどちらとも繋がりはなくローマを名乗っていたことだけが共通する。
何が神聖なのかわからないし
帝国の形態を為していない
そもそも何処がローマ的なのかと馬鹿にされてたからなあ…
というローマ変遷は人類史を語る上で非常に興味深い
イタリア半島くらいならギリギリ共和制でも行けたけど、版図が広がりすぎてスペインからシリア・イラクまで国土が広がったから帝政でしか統治できなかったんだろうな
中国なんか統一王朝ができた始皇帝の時代からずっと帝政だ。国土が広くて国民も多いからだ
今のロシアや中国が帝政と同様の専制国家なのも同様だ。アメリカは建国後すぐに通信技術とか教育とかのインフラが出来たから共和制で統治可能になったんだ
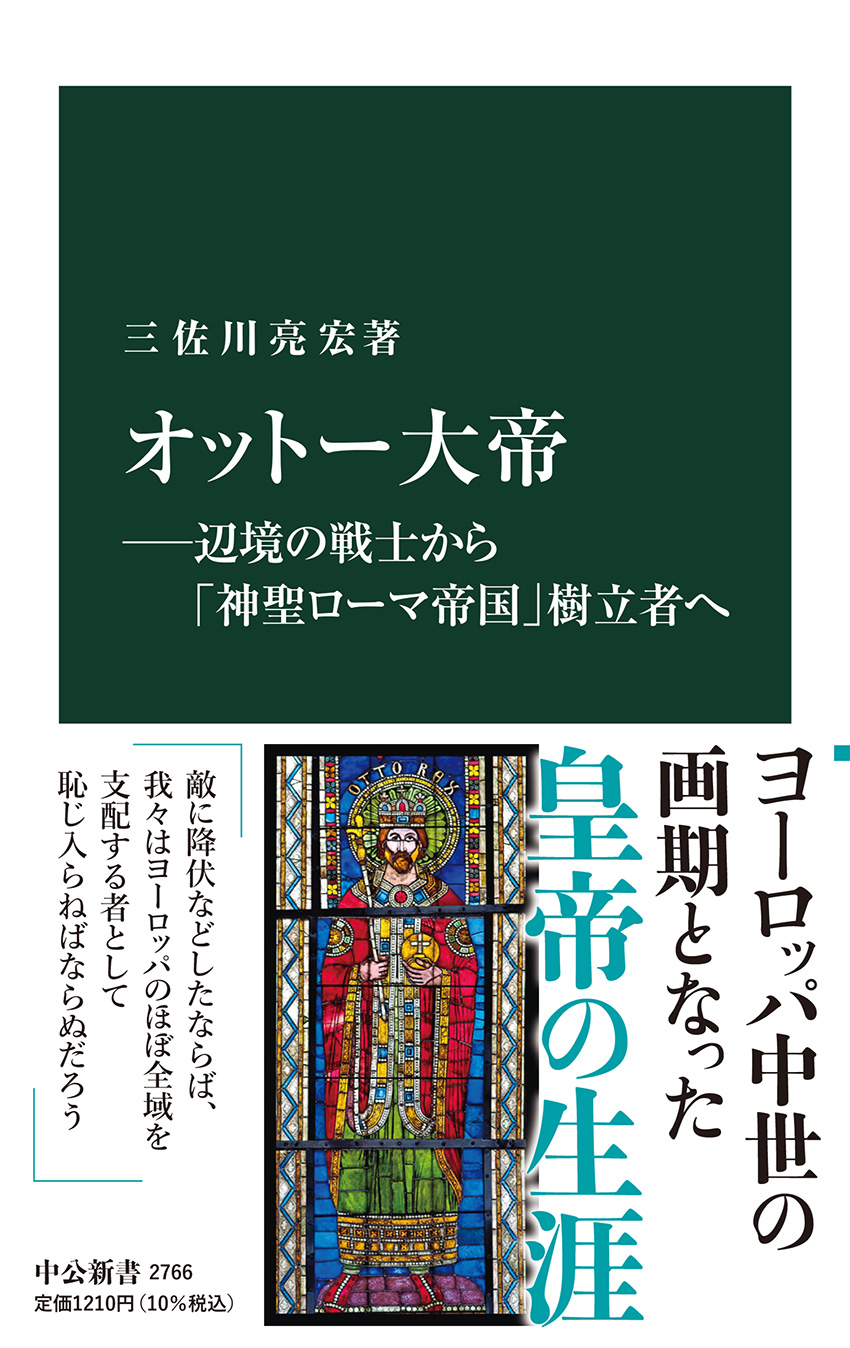
だからローマ帝国が続いてても微妙な存在だったと思うぞ。

衰退した帝国を支えたのはキリスト教のオカルトパワー
審判の日まで続く地上唯一の帝国という設定を作ってキリスト教の教義と帝国の統治を混ぜて正当化した
引用元: https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1692442458/
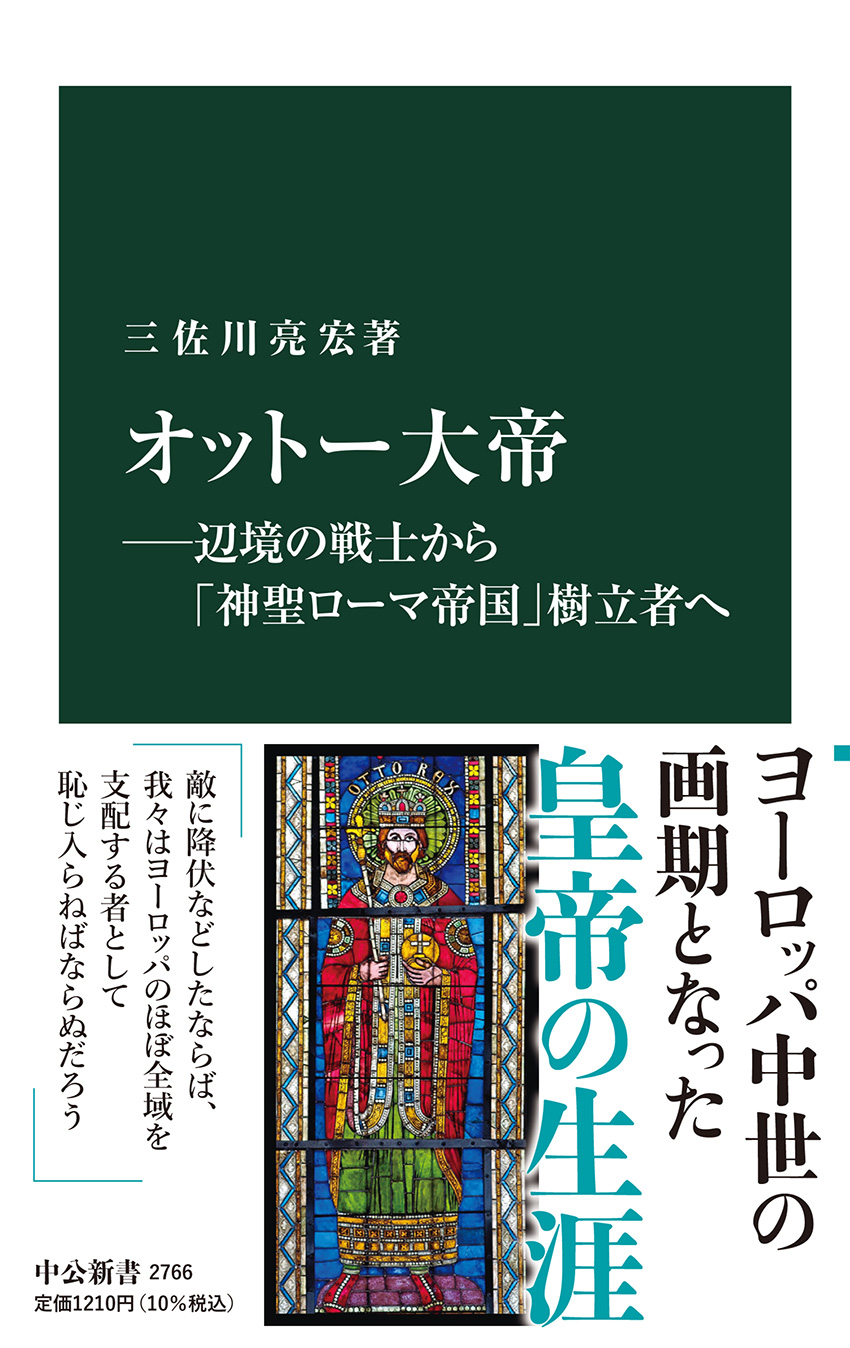
コメント