1: 2018/07/04(水) 23:10:28.60 ID:CAP_USER9
青森で忍術書が見つかる
江戸時代の弘前藩のものか
青森大(青森市)の清川繁人教授は4日、江戸時代の弘前藩で活動していた忍者のものとみられる忍術書が見つかったと発表した。
武器の説明や敵に狙われないための心得が記されており「忍者部隊の存在は文献には残っていたが、忍術書の発見で活動が裏付けられた」と話している。
清川教授によると、京都市の研究家が3月、青森県の弘前市立図書館で発見。
解読の結果、既存の忍術書には記載のない薬品の調合方法があり、弘前藩独自のものと判断。
カタカナを多用するなどの特徴から江戸時代に作られたとみられる。
全12ページで、刀の切れ味をよくするための呪術、眠り薬を作る方法などが記されていた。
共同通信 2018/7/4 18:44
https://this.kiji.is/387177474276918369
46: 2018/07/05(木) 00:13:44.04 ID:neIf1mVK0
>>1よりも詳細な記事
弘前藩忍者集団の書、図書館から発見 [2018/7/4 21:26]
http://this.kiji.is/387219128874206305
忍術書はB5判ほどの大きさで全12ページ。敵の目をくらます薬、
武器の作り方、建物に忍び込んだときや旅先の宿での心得などが記されている。
表紙をめくって左側の最初のページは「ヒキガエルの皮を8月15日の酉(とり)の刻に
はぎ取り、乾かした物で刀を拭えば、鉄や石といえども切れないことはない」としている。
甲賀忍者や三重県伊賀市発祥の伊賀忍者に伝わる忍術なども書かれているが、
独自の記述も多く、写本ではなく弘前藩オリジナルの可能性が高いという。
まじないの文言も 忍者集団・伝承の忍術書見つかる [7月4日 20時29分]
http://mainichi.jp/articles/20180705/k00/00m/040/034000c
火薬とトリカブトを混ぜて目くらましを作る方法や、乾燥させたヒキガエルや
オシドリなどを燃やして作る眠り薬など怪しげなものも。
忍者らしく、旅先での心得には「宿では使用する出入り口を1カ所にし、
侵入者に気付くように扉に畳を立てかけておく」などと指南されているという。
55: 2018/07/05(木) 00:19:14.48 ID:neIf1mVK0
>>1
清川教授によると、弘前藩は、アイヌが蜂起した1669年のシャクシャインの戦いで
アイヌと松前藩双方の情報を収集、国元を通じ幕府に戦況を報告したとされる。
その後、4代藩主・津軽信政が甲賀忍者の中川小隼人を召し抱え、早道之者が結成された。
しかし、家老・棟方作兵衛貞隆がタヒ去すると、政敵の圧力により1756年に解散。
この政敵の失脚後、早道之者は5年の時を経て再結成され、明治初期の1870年まで存在した。
これらの経緯を踏まえ、清川教授は、棟方家の関係者が忍術を
後世に伝えるために1756年頃に著した可能性が高いとみている。
漢字と片仮名を交えた文章からも江戸中期のものとみてとれるという。
清川教授は「早道之者は日本で最も大人数で組織的に活動していた。
伊賀や甲賀の忍者が江戸時代にはほぼ出番がなかったことを考えると、
弘前の忍者の独自性が光っている」と話した。
http://this.kiji.is/387219128874206305
57: 2018/07/05(木) 00:20:33.47 ID:CkbhVSEa0
>>1
図書館にある掛け軸の裏に…!?
それとも仕掛け扉か?どんでん返しか?
忍術所を内包する図書館…!いったいどんな建物なんだ!
教えてくれ!青森県民!はよ!はよ!
2: 2018/07/04(水) 23:12:02.40 ID:GmCQzjdB0
催眠術の記述はないかな?
8: 2018/07/04(水) 23:14:06.20 ID:6Ipm+iTW0
>>2
眠り薬を作る方法が書かれている。
76: 2018/07/05(木) 02:54:17.23 ID:1yF5vPiW0
>>8
ありがと。い、いや…別に催眠術とか眠り薬で変な事しようとか考えてなかったんだか興味本位でね。
ちょっと青森に旅行行ってこようかな…
4: 2018/07/04(水) 23:12:56.64 ID:jQyA4BiP0
市の図書館にあるような文献すら見つけられない研究者は何やってたの?
16: 2018/07/04(水) 23:19:20.41 ID:gAyHidtD0
>>4
江戸時代は文章がベラボーに多いので完全に読まれていない文章も多い。
鎌倉以前とかなら、そもそも文章が残っていないし、残ってる文章はほぼ読まれているから、文章だけで大発見なんてことはあまりないけど。
32: 2018/07/04(水) 23:32:29.36 ID:FOBZVtKL0
>>4
元は旧家の蔵に眠っていた文書みたいなのが一山いくらみたいな感じで寄贈されてそのまま図書館の倉庫に眠ってる
そういう何十年も誰も目を通したことのないような玉石混交な資料が全国にいっぱいある
そういうのをヒマな民間の歴史研究家()が読み込んでいろいろ見つけてる
69: 2018/07/05(木) 00:42:53.46 ID:tK1rxBLn0
>>4
弘前市の図書館はあなどれないんよ
弘前大学図書館の一般利用+弘前市図書館でちょっとした研究が出来るけど
民俗学やってる先生はまだいるのかな
6: 2018/07/04(水) 23:13:37.34 ID:cqFqwagU0
忍術所?
105: 2018/07/07(土) 09:54:57.44 ID:0Md1XY400
>>6
>忍術所?
一瞬ビビったよね。
そんな大規模なもんを見逃してたなんて馬○か、それとも巧妙に隠れ込んでいて発見不能だったのかと。
誤字と分かって凄い発見なのは変わりないのに、変なガッカリ感が半端なく漂うw
107: 2018/07/07(土) 11:27:57.24 ID:di6NiKh40
>>105
青森大学の忍者先生に聞いたとおろによると、弘前城下町に住んで、回りのみんなも「あの家は忍者やってる」って普通に知ってたらしいよ
対南部や対秋田だから、地元で公知の事実でもあまり問題なかったらしい
7: 2018/07/04(水) 23:13:44.72 ID:JUnTPYVZ0
江戸時代の忍者オタク著
9: 2018/07/04(水) 23:14:08.00 ID:hQUE1cGa0
拳銃は最後の武器だ
10: 2018/07/04(水) 23:14:35.04 ID:W53sj4z/0
図書館の地下に修行場が発見されたかと思ったじゃねーか
19: 2018/07/04(水) 23:19:49.43 ID:gAyHidtD0
>>10
スレタイの意味がわからず二度見した。
102: 2018/07/07(土) 09:49:18.72 ID:8/PUl3y10
>>10
全くその通り
11: 2018/07/04(水) 23:15:08.81 ID:tU649l1+0
この教授は弘前に「忍者屋敷」も発見してる
うさんくさいったらありゃしない
12: 2018/07/04(水) 23:15:35.51 ID:jQyA4BiP0
んでこの京都の研究者って何者よ?
青森大(笑)の教授とやらはマスコミに流す前にちゃんと論文書けや
70: 2018/07/05(木) 01:05:55.51 ID:e/yG6u8x0
>>12
意外なことに薬学部教授
勿論薬剤師持ちだが、自分の講義も研究は全くしないで、忍者の話ばかりしてるイカれてる教授
休講が多いので学生からは人気
79: 2018/07/05(木) 03:21:21.84 ID:8G4sGdnQ0
>>70
青森大学ってスポーツやってたやつが籍だけ置いてるイメージだったんだけど実体があるのか…
最近は休講した講義はちゃんと補講しないといろいろとお上が煩いはずだがここはそんなの関係ないの?
90: 2018/07/05(木) 11:47:08.34 ID:e/yG6u8x0
>>79
一応薬学部はある
国家試験合格率全国最低だがw
国の基準には詳しくないが聞いた話
休講まで行かなくても今日の授業は忍者の説明とか、今日は忍者実習をしますとか
でも津軽の忍者って、伊賀や甲賀みたいに隠れ里とかではなく、普通に弘前の町中に住んで格好だけ変だから、回りにバレバレだったらしいとさ
13: 2018/07/04(水) 23:15:44.96 ID:CAP_USER9
120: 2018/07/08(日) 07:54:45.28 ID:YbENSyM20
>>13
掛け軸が隠し扉になっていて
クルリと回転して秘密の抜け道から
外に逃げられるようになっている
と思ったじゃないか!
14: 2018/07/04(水) 23:18:07.18 ID:8olnDAOy0
お前らもメモ帳に萌え萌えキュンとか書いとけば数百年後にはニュースになってるぜ
17: 2018/07/04(水) 23:19:22.72 ID:LX+YajWF0
秘伝の書をめぐる各国エージェント忍者同士の壮絶な忍者バトルに
24: 2018/07/04(水) 23:22:34.07 ID:NkwHtB1d0
>>17
えー?甲賀伊賀風魔雑賀あたりならいざ知らず弘前だぞ?
そんなに大した情報ないだろー
31: 2018/07/04(水) 23:32:05.72 ID:SxXAeOYz0
>>24
美味しいリンゴの作り方とかいろいろとあるんじゃないの?
18: 2018/07/04(水) 23:19:46.37 ID:NkwHtB1d0
イタコ呪術で遠距離攻撃
忍者で近距離攻撃
弘前藩はタヒ角なしだな
20: 2018/07/04(水) 23:20:20.83 ID:LjdoMTe60
図書館に忍術所って危なくないか?
21: 2018/07/04(水) 23:20:38.23 ID:wUuyLVXe0
青森の図書館が忍術所だと思ったから、習いに行こうと思ってたのに違うのか
23: 2018/07/04(水) 23:22:32.22 ID:CBO7zB+X0
大本棚がグルっと回って、その向こうにすっげえ道場とか修行用の洞窟とかが出て来た
25: 2018/07/04(水) 23:22:39.36 ID:Igt1JK+R0
江戸時代は天下泰平だったはずなのに、藩の諜報部隊はやっぱ活動してたのか
27: 2018/07/04(水) 23:25:51.30 ID:0S7UC9as0
>>25
諜報部隊はいついかなる時でも重宝するからな・・・うーっくっくっくっ
33: 2018/07/04(水) 23:32:38.58 ID:UWplyBMs0
>>25
お上の動向探るのが主な任務だったろうな。
江戸時代の初期は、改易ラッシュだったから。
外様は戦々恐々だったろう。
28: 2018/07/04(水) 23:26:33.87 ID:yDftKSlF0
青森には、戦国時代にヨーロッパから入ってきた、
トランプの賭け事が生きていて、あまりにも熱中するので、
禁止になったようですね。想像以上に戦国時代や地方というのは、
外国の影響を受けている。
29: 2018/07/04(水) 23:29:01.10 ID:yRq+siy+0
>>28
伊達政宗の頃に輸入したのか
51: 2018/07/05(木) 00:16:25.31 ID:dfdz7xwH0
>>28
南蛮妖術 母如礼縫亡(ボジョレー・ヌーヴォー)?
30: 2018/07/04(水) 23:30:55.52 ID:UWplyBMs0
>刀の切れ味をよくするための呪術
コレは是非公開して貰いたいな。家庭の文化包丁の切れ味を復活させたい&長持ちさせたい。
50: 2018/07/05(木) 00:15:21.15 ID:PPaLTJ8/0
>>30
お侍様は庭に砂の山を用意していて
出かけるときには刀をその山に突っ込んでから行ったそうな
いわゆる寝刃を合わせるという作業の変わりやな
お前も台所に砂山を置いておいて使うたび突っ込んでろ
71: 2018/07/05(木) 01:14:00.04 ID:F7HS7aoC0
>>50
砂山かぁ…猫のトイレくらいしかないが、衛生的に(ry
115: 2018/07/08(日) 06:36:12.66 ID:TXqpefBl0
>>50
うちの痴呆婆はオレが買った8千円の包丁を畑に放置してサビサビにしてしまったが
オレの攻撃力を削ぐことを狙ったくノ一なのでは
34: 2018/07/04(水) 23:34:47.78 ID:8qmcUgqv0
海外のオークションに出せよ
35: 2018/07/04(水) 23:43:08.03 ID:6UEZRrib0
こういうのってニセモノも多いから多元的にしっかり調査しろよ
本物だったら、中の悪い南部藩に忍び込んだりしてそう。ネガティブな情報を幕府にリークしたり
37: 2018/07/04(水) 23:52:38.88 ID:Yinf8yza0
うちにもあるわ一族に伝わる忍術書
世に出すつもりはないけど
38: 2018/07/04(水) 23:54:52.38 ID:yDftKSlF0
>>37
情報収集とか情報発信などが多かったようですけど、
どんな内容なんでしょうかね。
40: 2018/07/05(木) 00:01:01.17 ID:NaqJ9lgL0
でっかいカエルに乗ったりするやつは何ページ目に書かれてんだよ
42: 2018/07/05(木) 00:10:13.95 ID:x4mn2uYx0
43: 2018/07/05(木) 00:11:38.07 ID:Nk6FTmEr0
津軽弁は本来暗号として生まれた
忍者の末裔である青森県民以外は解読出来ない
45: 2018/07/05(木) 00:12:32.86 ID:XfIL9Q5a0
胡散臭い情報と、入り口は一ヶ所に絞ってそれ以外には畳でバリケード作っとけ、とか比較的実用的な
戦術とが混ざってる辺りに忍者っぽさを感じる
52: 2018/07/05(木) 00:17:14.38 ID:tih5E8WB0
弘前出身だが、弘前番地なんて聞いたことないわ
津軽藩じゃねえの?
74: 2018/07/05(木) 02:24:34.74 ID:w4zifwpc0
>>52
「弘前藩庁日記」っいう有名な書物もあるから、正式には弘前藩だと思う
100: 2018/07/07(土) 09:34:52.18 ID:yEXAaWD/0
>>52
ウィキペディアを信じるならば正式名称が弘前藩でその藩の俗称が津軽藩らしいぞ
あと確かさくら祭りで見た弘前城の案内施設だと弘前藩使ってた
54: 2018/07/05(木) 00:17:34.46 ID:zexGTjBS0
山田風太郎がアップを始めました
60: 2018/07/05(木) 00:26:34.68 ID:FlaKV0YK0
図書館の取り壊しで発見されるとは思ってもみなかった。
63: 2018/07/05(木) 00:31:52.33 ID:oU6o72520
訓練部屋でも見つかったのかと思った
64: 2018/07/05(木) 00:33:22.82 ID:EP74xWDm0
写輪眼はよ
65: 2018/07/05(木) 00:37:16.25 ID:T2SeL2yD0
伊賀と甲賀以外にもいたのか?
本州最果ての地に
86: 2018/07/05(木) 06:18:04.21 ID:KLAgxifvO
>>65
津軽藩が甲賀忍者の一人を召しかかえた
91: 2018/07/05(木) 11:49:18.74 ID:e/yG6u8x0
>>86
石田三成>たつ姫繋がりだしな
まて姫とたつ姫の津軽関ヶ原の戦いとかしょうもない忍者の暗躍があったとか
73: 2018/07/05(木) 02:08:13.36 ID:w0Gcc28K0
12ページぐらいなら
さっさとスキャンして
国会図書館で公開しろよ
75: 2018/07/05(木) 02:46:54.22 ID:hHbJVHH30
しかしこういうの人工知能にさくっと読ませて分析できないのかね
77: 2018/07/05(木) 03:04:50.35 ID:OTgF2ONg0
信長の野望で安東家や津軽家の知略がまた上がるな
80: 2018/07/05(木) 03:29:41.96 ID:fy/s224o0
忍者で町おこし
81: 2018/07/05(木) 05:57:43.65 ID:i+9ot0qx0
上方の情勢をいち早く知ることで独立した津軽氏だから情報の重要性は藩の共通認識として受け継がれたんだろう
忍びは江戸藩邸に詰めて情報を探ってたに違いない
84: 2018/07/05(木) 06:11:18.61 ID:8aLfrEVU0
元々城下町だしな、忍術書があってもおかしくはないか
88: 2018/07/05(木) 06:41:40.77 ID:n0DzIomw0
この手の新発見を頭から否定するわけじゃないけど、
江戸時代となると本物の忍術書じゃなくて、
講談や読本で知識を仕入れた忍者マニアが書いた
同人の設定メモとかの可能性もあるんじゃないかなぁ。
そっち方面でも歴史資料としての価値はあるだろうけど。
93: 2018/07/05(木) 16:10:59.36 ID:d/tf90Od0
青森の忍者じゃさほど腕利きっぽくない印象になるのはなんでだろ・・・
95: 2018/07/05(木) 16:31:07.95 ID:qOY0+vLo0
>>93
相手が天下や幕府じゃなくて、南部(青森県東部)という超どローカルな戦いだからな
96: 2018/07/06(金) 00:38:50.09 ID:SYb53EX10
>>95
東北もそれなりに有名な戦・史跡・武将がいるんだけど、
主にコーエーが東北に限って武将を干しまくり、史実を紐解かない怠慢の姿勢を保ってたせいで
豊臣が来るまで平和な田舎だったと勘違いされてるんだよな…実際はガンガン争ってたってのに
97: 2018/07/06(金) 01:02:26.55 ID:vulcZHep0
>>96
いるんだけど中央の歴史に絡んでないからな
日本全体を動かすような武将や戦いがないと厳しいよ
縄文時代まで遡れば三内丸山が…
104: 2018/07/07(土) 09:50:49.10 ID:vqsPIsBZ0
>>93
戦国最強と言われるのは越後兵だし島津も地元限定なら中央の兵を圧倒したし田舎だから能力が低いとするのは早計だろ
94: 2018/07/05(木) 16:16:11.66 ID:fMginiIg0
忍者なくて修験者が書いたんじゃねの
98: 2018/07/06(金) 09:42:55.57 ID:8/nZ24HI0
たった12ページかよ。薄い本だな。
99: 2018/07/07(土) 01:44:11.94 ID:tkbAe3Mi0
忍者の実態とかは知らんが、平和な時代とはいえ情報収集は、あらゆる手段を使ってやってたんじゃないの?
20年ぐらい前に弘前の高照神社の宝物を展示してる所を見学したら、江戸時代に制作された全国の城や城下町の詳細な地図を展示してた。
城内の配置とかも描かれてた。
商人とかから普通に購入しできたのか、あるいは当時は幕府に城や城下町の工事を事前に届ける必要があったから
幕府内部の人から入手したのかも。
入手の経緯は知らないけど、かなり他藩の動向を気にしてたのは、その展示物の地図からは感じられた。
他の藩もそういう情報収集はやってたと思うよ。
今に残ってないだけで。
一番大きい徳川将軍家の締め付けがあったどろうけど、それでも各藩は独立した国みたいなもんだったんだな。
106: 2018/07/07(土) 09:57:36.08 ID:0Md1XY400
>>99
入手経路が購入であれ情報収集には変わりないからな。
今のようにAmazonがある訳でも郵便がある訳でもないし。
しかも見方を変えれば、詳細な見取り図が単に買うだけで領内に持ってこれるっては凄い効率的な活躍でもあるよね。
109: 2018/07/07(土) 18:40:34.34 ID:9Z7wkeYi0
忍術書といっても、火薬とか毒薬など製法や使用法の知識を記したものだったり、
教育勅語のような諜報部員としての精神論や、忍者として潜伏するための
普段の生活の心構えや注意点などにすぎないかもしれない。
そのほか医学的な知識(薬草、病気の治療法、予防法など)
この呪文を唱えたら変身できるとか、ガマを巨大化するとか、目で催眠術を
かけて幻惑するとかそういうのは多分ない。
114: 2018/07/08(日) 06:23:09.02 ID:AGGYsauU0
文章に残ってる奴は忍者が必要なくなったから文章にしたんだよな
116: 2018/07/08(日) 07:30:10.44 ID:ijY4anXN0
幕府の黒鍬衆も忍者の系統の足軽身分だけど、黒鍬と分かる格好で江戸のまち中とか人前歩いてたよね。
117: 2018/07/08(日) 07:31:32.14 ID:ijY4anXN0
半武士身分の黒鍬と違って、武士身分の御庭番は、普通の武士の格好や町人の変装とかしてたろうけど
118: 2018/07/08(日) 07:32:25.36 ID:ijY4anXN0
鉄砲衆の雜賀衆も忍者だし、何をもって忍者なのかは
130: 2018/07/08(日) 08:14:28.81 ID:zEapJ+Q60
>>118
雑賀衆もそうだけど伊賀衆なんかも結局は傭兵集団だったりするからね
言われるほど忍んでない
暗○や潜入調査もやるからそういう仕事を専属でやってた奴も中にはいるかもしれないけど
119: 2018/07/08(日) 07:39:40.24 ID:ijY4anXN0
黒鍬者と呼ばれた黒鍬衆、はじめは半武士の足軽中間身分だったが
後には、武士身分の同心格になったけど。
黒鍬組頭は上級御家人の与力身分。
121: 2018/07/08(日) 07:56:56.62 ID:rwB5okI40
拙者の心の片隅にはいつも忍術所があったでござる
122: 2018/07/08(日) 07:57:52.41 ID:lL6mWg+p0
分身の術を是非公開してくれ
123: 2018/07/08(日) 08:02:00.93 ID:bZMv6sdD0
>>122
アルヨ。
126: 2018/07/08(日) 08:05:25.11 ID:lL6mWg+p0
>>123
すげー速さで出してきたな
124: 2018/07/08(日) 08:02:46.38 ID:Y1f44D8v0
忍犬もたくさんいるんだろ?
125: 2018/07/08(日) 08:04:57.79 ID:JbgL6MP10
ここに書き込みしてる奴の中にもいるだろ?
部屋に忍んだまま社会に実態を見せない現代の忍者が
128: 2018/07/08(日) 08:08:10.02 ID:EgmzZbUW0
>>125
せ、拙者蝶のナイフなぞ知らぬでござるよ
127: 2018/07/08(日) 08:05:58.26 ID:D+O5D/t50
国防防災に役立つ火遁の術と水遁の術を学校で教育しろ
129: 2018/07/08(日) 08:13:04.92 ID:Z7ddgMNE0
螺旋丸と多重影分身がありゃ大抵解決出来る
131: 2018/07/08(日) 08:14:56.91 ID:rwB5okI40
風呂上がりにはフリチンの術が勝手にでちゃうでござる
132: 2018/07/08(日) 15:46:57.30 ID:TXqpefBl0
妖術とか後付のファンタジーと思ってたけど実際に書かれているのか
133: 2018/07/08(日) 15:47:32.88 ID:/TwI8s500
江戸時代のラノベでしょw
134: 2018/07/08(日) 15:50:42.78 ID:YI2S9cIo0
図書館の奥の本棚の左を強く推すとあら不思議、棚が回転した奥には隠された「忍術所」なる部屋が!
という展開ならよかったのに
引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1530713428/

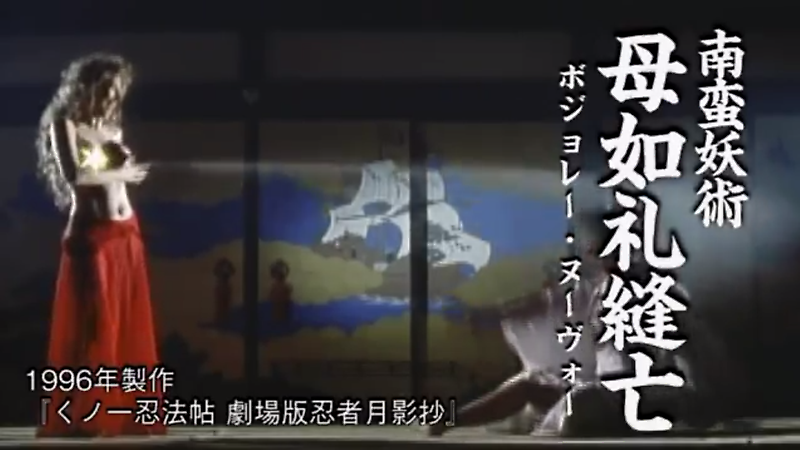

コメント