https://news.yahoo.co.jp/articles/8da842231de5230939e2f442dc1dc27ec4313338
須玖岡本遺跡から発見された石製の「権」。右が10倍権、左は30倍権=福岡県春日市の奴国の丘歴史資料館で2021年9月1日午後3時38分、上村里花撮影

https://cdn.mainichi.jp/vol1/2021/09/01/20210901k0000m040353000p/0c10.jpg
福岡県春日市の須玖(すぐ)遺跡群・須玖岡本遺跡の出土物から、弥生時代中期(紀元前2世紀~同1世紀)とみられる石製の分銅「権(けん)」(最大長5センチ、最大幅4・15センチ)が新たに確認された。1日、市教育委員会が発表した。朝鮮半島南部で発見された権と共通の規格で作られたとみられ、基準となる権(約11グラム)の約10倍の重さだった。同規格の弥生時代の10倍権が確認されたのは国内初。市教委は「弥生時代から国内でも10進法が使われていたことを証明する重要な発見」と話している。
遺跡群からは2020年、国内最古級となる弥生時代中期前半~後期初め(紀元前2世紀~紀元1世紀)の権8点が確認された。これらは韓国・茶戸里(タホリ)遺跡の基準質量の▽3倍▽6倍▽20倍▽30倍――にあたり、権に詳しい福岡大の武末純一名誉教授(考古学)は10進法が使用されていた可能性を指摘していた。今回の発見で、その可能性がより高まった。
武末名誉教授によると、これまで古墳時代に10進法を使用していたと考えられる事例はあったが、弥生時代に関してはそうした観点での研究はなかったという。
須玖岡本遺跡は、中国の歴史書「魏志倭人伝(ぎしわじんでん)」に登場する「奴国(なこく)」の王墓とされ、同遺跡を含む須玖遺跡群は青銅器やガラス、鉄器などの生産工房跡も多数確認されている。当時の先端技術都市として「弥生のテクノポリス」と称される重要遺跡だ。市教委は「権は材料の調合のために正確な計量が必要だった青銅器の製造などに使われていたと考えられる」と説明している。武末名誉教授も「10進法の使用は奴国の先進性を裏付けるものだ」と話している。【上村里花】
紀元前1~2世紀は縄文時代だよね? 紀元1~2世紀なら弥生時代だけど…
記事中の紀元表記か時代表記のどちらかが間違ってるよね?
紀元前後300年ずつ、都合600年ほどが弥生時代と覚えるといい
ただし、あなたが新説を唱えるなら話は別
弥生時代の始まりは紀元前4世紀と言われていたが、最近では紀元前10世紀くらいまで遡ると言われている。
ベムかw
数が数えやすい10進数が普通
12進法はやはり指が12本ある異星人が関与してるのだろうか?
円を等分するにしても8か16が合理的に思えるけど12の由来って判明してるのかな?
1年が365日→約360→円の角度360度→30度×12
360°は人間が勝手に決めただけだろ
>12の由来
一年に月が約12回地球を回るのがおおもと
角度の360度も一年約360日から来てる
約数が多いからでは?
世界的にはどうなん?
10進法が多いけど、15進法やら6進法やらもある。
http://www.sf.airnet.ne.jp/~ts/language/numberj.html
片手で31、両手で1023まで数えられる。
本当に?
指がつりそうになるけど
趣味でギターをやっていた俺には余裕。
中国も周王朝時代に利用していたとか
古代エジプトはナイル川の洪水後土地の境界決めるために幾何学や測量術が発達した(ピラミッドはその集大成)
とか言うからな
中学高校の授業で数学史とりいれたら数学嫌いの人間減ると思う
三等分できるか、四等分できるかが重要で、
辛うじて視認できる12が便利だった。
60は視認できないからな。
商取引が活発なところは12進数だな。
多分、10倍という発見は偶然の一致だろう。
時刻は12進数だし、干支も12個だな。
分や秒は60進数ではあるが。
12進数は月の満ち欠けからの12か月からきてると思う
これを細分化すると60進数にいたる
角度の360゚は1年365日から
1ヶ月が30日なのは月の満ち欠けが28日から
1週間が7日なのは、月の28日を割り切れる2,4,7,14から
大体人のサイクル的にちょうど良い7を選んだんだと思う。
(新月→半月→満月→半月→新月で分かりやすいってのもある)
紀元前3世紀に始皇帝が度量衡を統一し
全国に標準化された分銅配ってるから
10の約数だし、片手の数だし
10進数とかいう概念は持っていなかったはず
ただの偶然
基準とする重りに対して重いか軽いかだけの概念しか持たない程度だろう
両指で数えられなくなった時点で
位取りが必要になるから
手が基準が10進数でいいと思うが。
割り算の必要が増えて初めて気がつく事実。
割り算使わない歴史が長いと10進で進む。
古代の王への租税って収穫物がメインだったろうから十二進法のほうが使い勝手がいいよね
半分納めるのならどちらでも構わないがこれが3分の2とか3分の1とかだったら
十進法では小数点の足が出るので何かと不都合
ひとつ ふたつ hitotu hutatu
みっつ むっつ mittu muttu
よっつ やっつ yottu yattu
と倍数になっているのも興味深い
なるほどおもしろい
1秒が60個で1分
1分が60個で1時間
1時間が24個で1日
この辺から
1日が適当数で1月
1日が適当数で1年
辻褄合わせるために都合でうるう年
うるう秒も入れちゃえw
時間概念適当すぎ
時間と日付と天体運動の概念は別
一周360度は、一年365日に由来するのはガチ。
なぜ金は4進法になり銭は10進法になったのか
扱いが違うのは気になるよね
ホントに銅銭を銀に両替してくれるのかな・・・
気になるよなー
これから10進法が使用されていた可能性がわかるものなの?
組み合わせて使えば、そうなるね
アレかな、銅鐸も重りなのかな?
体重でも計ってたりして
7進法というと、1週間が7日なのはそこからか
日本でこれが採用されたのは明治になってからで、
それまでは別の思想に基づく暦が使われたみたいだな
英語もツェンティ、サーティで10毎に数詞が切り替わってるから、、十進法なのよ
12進法なら1ダース、1グロスなんだが、、13や14の数詞が有るから12進法だったとは言えないね
商取引用の梱包単位だったんじゃね
人間は生得的に3までは理解出来るらしいから>>253がしっくりくる
3は発明だよ
片手に1、両手に持つと2、両手に持てないのがあると3
3を発明できなかった部族は1,2,たくさんだから
Hi ×2 = Hu
Mi ×2 = Mu
Yo ×2 = Ya
これこれ
最初知った時感心した
月の満ち欠けを見てたら1年で12回満月があるらしい
じゃあ12を基準にしよう
そんだけ
ソレは四季の影響の無いクソ暑い中東の数え方やで
ソレと広い交易を持つと日数の打合せにお月さまが有効だったからじゃね
四季がしっかりしている所は、太陽の角度で周期を記録しないと困るからね、天文台が進法している所は太陽暦
中国は中東との交易で中東に合わせる必要があったのと、中東の文化な仏教の影響から太陰暦
3より大きい数字が数えられるなら、
10進法は使ってて当たり前。
指折り数える時に10までは数えられるから。
印欧語族・アフロアジア語族の古い言語の文法には、単数、双数、複数がある。
1・2は数詞としても、4以上の数詞(文法的には名詞・形容詞)とは明らかに文法的性格が違う。
これは、古い時代の地中海・西アジア方面の人の数感覚が、1つ、2つ、沢山だった名残。
日本語「さんびゃく」
私「…さんびゃく…よんびゃく…」
日本語「よんひゃく」
私「…よんひゃく…ごひゃく…ろくひゃく…」
日本語「ろっぴゃく」
私「(…『ぴ』?)ろっぴゃく…ななぴゃ…」
日本語「ひゃく」
私「…ななひゃく…はっひ…び…ぴ…」
元々はパ行
(´・ω・`)
>基準となる権(約11グラム)の約10倍の重さだった。
煮炊きする時の水の量とか、
保存、あといろいろな食材の分量、割合とか
何かで計量するのは絶対にやってると思う。
ほか砂金とか揉めないように対応表が作られていたり。
縄文時代眺めるのも暇つぶしになりそう
土器って乾燥して1割、焼いて1割、長さ的に寸法が減るんだよ。
きっちり1割減るんでなくて、結構バラつきがある。
物によって一つの器の右と左上と下で縮み方が大きく違うこともある。その場合はヒビが入ったり割れたりする。
土器で計量とかはとてもじゃないが無理。
古代・中世の為政者の度量衡の統一の際も、升は木製が基本だ。
木製でも計量容器が見つかると面白そうだね。
あと長さの単位。
その何倍とかの区切りで色々なもの、
柱とか家とか家具とか長さの割合がわかれば十進してるか解る。
獲物を何匹、何羽仕留めたか、
縄文小学校学校の入学問題、粘土板が発掘されたらすごいことに
農作物・農耕具・建築様式・青銅器等など持ってきてそこだけ違ってたらおかしい
引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1630509331/
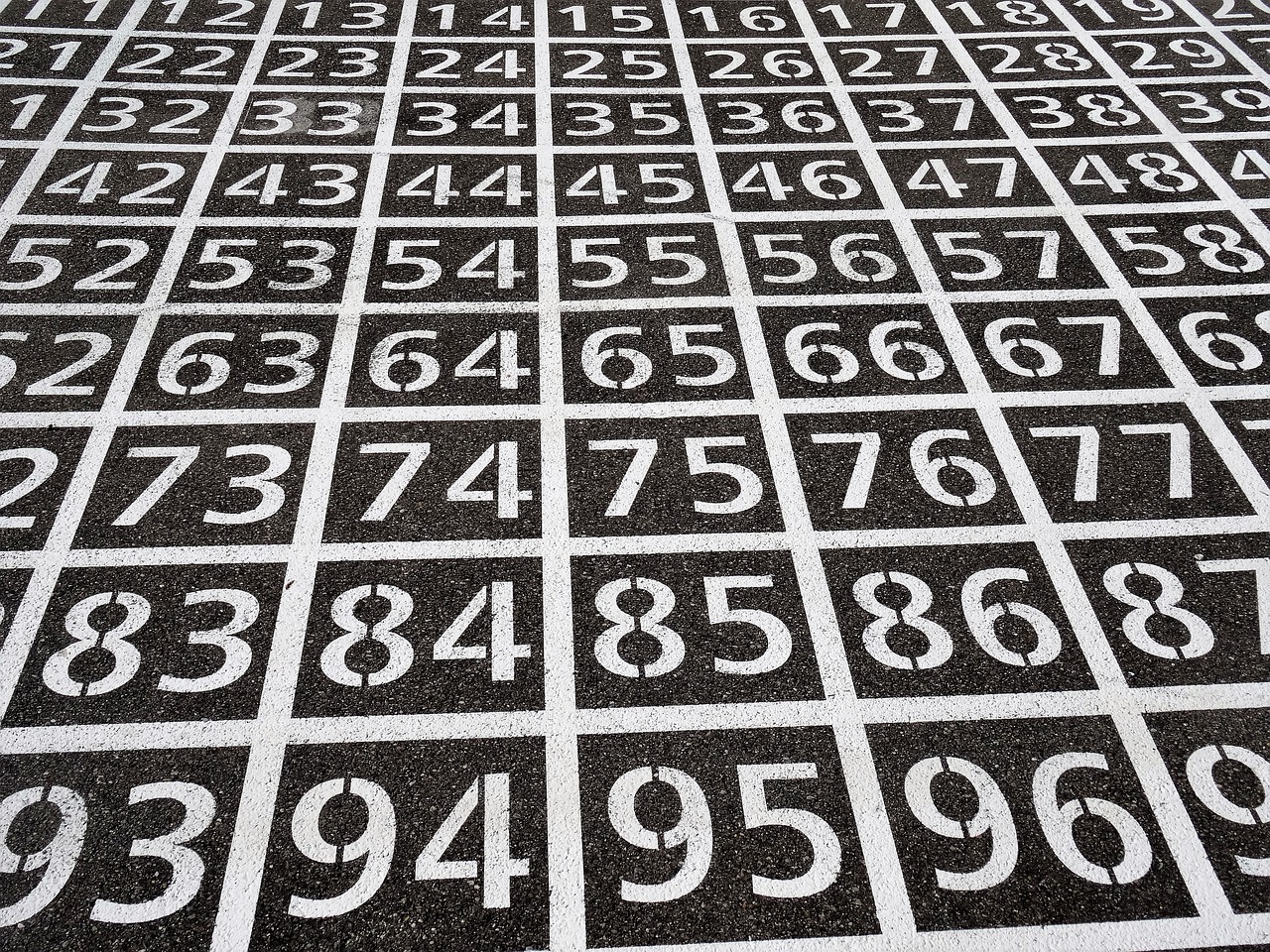
コメント