江戸初期に朱子学が官学になるのと三国演義が入ってくるのとほぼ同時で、
さらに寺子屋レベルでも朱子学をやってるところに三国演義が翻訳されて大流行すれば
儒学者から庶民まで含めた孔明評価の主流は自然と朱子学に基づくものになるはず
林羅山が知られる限りで日本最初の演義読者だった事は象徴的と言える
ただ、古義学の学者らは朱子学に基づく高評価に反論して孔明には王佐の才は無いとした
「孔明は無能」と言ったんじゃなくて、自ら覇者になる気配があったから
輔佐として評価が下がる、という論調だったと思う
ということで>>1を援護したいなら伊藤仁斎の文集でも読むと良い
だろうね。さっきも書いたが戦略、戦術云々言ってる人は朱子学のこと知らないんだろうね。
ここでは朱子学の思想に基づいての評価されてについて論議してるのを
分かってるのかな?
>朱子学は一種の思考の停滞を生む俺は好きではないし評価もしない。
自分も朱子学は嫌いだな。
個人的には負け犬の遠吠えか負け惜しみの学問、思想って感じがするし。
陽明学の方が好きだな。(まあ朱子学に反発?して出来た思想なんだが…)今更ながら言うが>>1自身はきちんとした主張とかないのかな?
諸葛亮&朱子学についての話を軸にして、
妙な風に脱線しなけりゃ軽いノリもいいと思うよ。
学問の堅いイメージがあるから構えちゃってるのかもしれないし。
>>10の様な素朴な話題から話が盛り上がるといいなぁと個人的には思う。
貴方のレスの大東文化大の渡辺先生が云々の話からでも、
なんだそりゃみたいな感じで話題が広がりそうだしwしかし>>3や>>7みたいなのが出てこられても、
そりゃスレ違いだって言われても仕方ない。
ましてやID:hwLSGBbB0みたいなのは話にならないしw
>>3
「道徳」としては悪くないけど「政治思想」としては村落共同体ぐらいの
為政者と住人の顔が見えるぐらいの規模でないと通用しないと思う。
朱子学などの新儒教は道教や仏教などの世界観と
世界を説明する理屈をパクって取り込んだ思想なので
元々の儒教とはかなり異なった存在になってます。
鎌倉期以来の儒学の研究テーマだったし
真面目に話し合う事には意味があるぞ
宋学VS古義学の論争に関係する問題であって
単なる儲VSアンチの厨対立に還元される話とは違う
一応、戦術面では魏と良く戦えていたからね
敗因も、兵糧の輸送能力の問題で、
(これについて本人も試行錯誤はしているが結局根本解決には至っていない、
マイナスポイントか)
彼が直接指揮した部隊は野戦・撤退戦では負け知らず。
(晋書宣帝紀の記述を無視すればね)
その勝利が戦略的に敵を震撼させるに至らなかった。
戦術的な勝利を戦略的な勝利につなげていけなかったのは、
彼の資質の問題に加え、魏蜀の国力差の問題もある。
そもそも彼自身荊益両州おさえて、はじめて魏に対抗しうると考えていた。
彼が益州一州で魏を打倒できると思っていたかは、疑問の残るところで、
仮に魏を打倒出来ると踏んでいたとしても、
一方で、
蜀漢が漢朝再興を謳い「反魏を掲げた以上は国家の存在意義を示さねば」という考えがあったとは思う。
おおむね同意。
魏延の乾坤一擲の進言を退けて手堅い戦略を採用したのも
彼我の体力差を考慮して着実に版図を広げていく展望だったのだろう。
涼州を確保できれば漸く魏主力と対決できるだろうから。
曹操側がまけると手を打って喜んだとあったよな。(宋代だったっけ?)>>9
逆にいうと、魏の側は戦略的勝利条件を築き上げて「多少の戦術的敗戦はどうでもいい」
くらいに思っていたのかも。
講談で聴衆が劉備側が負けると悔しがって、
曹操側が負けると手を打って喜んだって話はたしか宋代の頃だと思うよ。
あと戦術的云々はこのスレの趣向とは別の話だから
出来れば自重してほしいのだが…
民衆の場合は朱子学の思想よりも判官贔屓がもとだと思う。
>「多少の戦術的敗戦はどうでもいい」
司馬仲達がそうだな、負けてもいいとまでは思ってないだろうが
防御に徹して持久して蜀が力尽きて撤退するのを待つ。
かくいう孔明自身は実はガチガチの法家主義者。
同系らしいけど具体的にどの観点で諸葛亮賞賛が強調されてんの?
別に史学専攻でもなんでもないんで興味でちょっと読んだけだけど、
陽明学て古典経書に対する妄信アンチみたいな感じ?
格物致知的なトコで諸葛亮賞賛にあたるのかな・・
儒教と容れないタイプの思考だよねこれ。孔明の戦術どうこうとかこの話題と関係ねーんじゃねぇ?
似たようなこと腐るほど書きつくされてそうだし。
朱子学の教義的には、軍事的才能が不可欠ではない。
その点では十分合格点もらえるでしょ?生前の行動
つっても、蜀贔屓が朱子から始まるって分けじゃなくて、朱子以前から蜀贔屓はあったから、あくまで理論的根拠ね
孔明の過大評価の原因は演義のせいでしょ
朱子学では国の支配者を王者と覇者に分けてるから、
蜀漢は王者の理論に則っる国の正当な支配者=王者
曹魏は武力をもって支配する不当な支配者=覇者
として捉えてるのでしょう。
また王者の理論では、
この国の正当な支配者(この場合は蜀漢)は我々であり、正当なる支配者は常に絶対の正義である。
反抗するものは常に絶対の悪である。(この場合は曹魏)
従って悪は滅ぼさなくてはならない。
当然ながら正義である支配者に忠誠を尽くすのは絶対の善になる。
大義名分論と王者の理論の両方に当てはめてみても、
諸葛亮を生前の行動はやはり賛美の対象になるでしょうね。>>15
>孔明の過大評価の原因は演義のせいでしょ
そもそも演義自体が朱子学の影響受けてるし、羅貫中自身がかなりの蜀漢贔屓ですよね。
演義は評価をさらに引き挙げた要因の一つには間違いないでしょう。
陳寿の『三国志』をはじめ北宋の司馬光の『資治通鑑』などの史書では、献帝から禅譲された曹魏を正統としていたのに、異を称え蜀漢正統を主張したのもこの朱子なんだよね
だから、当然朱子は曹操や曹丕を逆賊だと非難してるし、この朱子学が以後官学としてメジャーになるから、官僚たちの間でも朱子の考え方が常識になる
これと『三国志平話』以来の民衆による蜀漢贔屓が合流・結合して生まれたのが演義じゃないかな
諸葛亮を過大評価しないとどうなるかという話をしてなにがおかしいんだ
スレタイは『朱子学で過大評価されてる』であって
軍事の話ではない。
軍の指揮官としては無能でも、朱子学的に評価される人はいる。
朱子学と軍事は、切り離せない関係ならともかく、そうではない。
諸葛亮は武の方面では、過大評価されてる。では文の方面では?
儒者としては評価されても、政治的には無能な人物はいる。
その逆に、倫理的に問題がある大政治家だっている。
諸葛亮は完全無欠の政治家だったのか??
かくあるべし!!と理想を重ねられて、実像と離れたキャラにされてないか?
馬謖に対する処罰は適性だったか?
別に軍事面に限らなくても、過大評価されているか、否かは、判断できる。
逆に諸葛亮の軍才を朱子学の観点から、どのように評価するのか知りたいが。
まあまあ、そう興奮せずモチツケ
>>21は朱子学のことよく分かってないんでしょ?
朱子学って別に軍才を評価の対象とする学問、思想じゃないんだし。>>25
朱熹が再構築した儒教の新しい学問体系として、
提唱してるのは南宋期になるね。
完成と言っていいのかは、微妙。
朱熹自身がこの論を完全な物として納得しているのかがよく分からないし、
もしかしたら朱熹自身その論を
更に高みに押し上げようとしてたかもしれない。
と言うのが個人的な主な理由。
27とかは三国志しか知らないんじゃねーの?朱子学がなにかもさ。そもそも朱子学自体十分その限界がとおの昔の指摘されてるんじゃねーの。
今更朱子学的に諸葛亮みたいのや王導みたいなのがすばらしいから彼らは
無欠だとか今日び無意味。 王導は優れているけどさ。
朱子学は一種の思考の停滞を生む俺は好きではないし評価もしない。
そもそも戦国以後の思想はそういうものが多い。閉塞的。
「天才軍師孔明」ということなら、朱子学は関係なさそうだし。
これは、巷間から生まれたヒーロー像ぽいからなぁ。
中国のよりおだやかな感じがあって、それが孔明論にも反映してる気がする
江戸の風俗本で劉備や孔明が吉原で遊ぶ話があるが
本家の朱子学を峻厳に貫いてたらこんな本は庶民レベルでも多分ありえない
大塩平八郎の例をみても陽明学のほうが峻厳な感じやね
庶民レベルでは朱子学はあまり関係しないんじゃないの?日本でも中国でも。
演技の孔明像は朱子学的な評価とはまた別系統のものが入っているだろうし。
日本の朱子学と云えば水戸学ではないでしょうか?
(水戸学は結構、峻厳だと思う)
徳川光圀が朱舜水らとの交流を通じて、天皇による普遍的な統治が続けられた
日本こそが中華思想の説く正統な国家であるという意識を持っていた様で
彼の著書である大日本史は全体的に大義名分論の尊皇思想で
貫かれていたことから、水戸藩は、水戸学によって、
天皇を尊ぶ尊王思想の気風を植え付けたともいわれてますね。また水戸学は、江戸幕末の尊王攘夷運動に強い影響を与え、
明治維新の原動力の1つにもなったみたいだし。
水戸学の強い影響で徳川慶喜はバリバリの勤王派だったし。(慶喜は元は水戸家の出身)
あと後醍醐天皇も朱子学に強い感銘を受けてるし。
(諸葛亮とちょっと関係ない話でスマソ)
>>34
演義の中の諸葛亮は明の劉基(劉拍温)がモデルになってると言われてますね。
その劉基は蜀にいた趙天沢が彼はして「諸葛亮に類する」と評していますし。
あながち関係なくもないですね
王権を簒奪した「周の粟」は口にしないと言って会稽山に籠もり、
餓タヒした伯夷・叔斉の行為と謝枋得の行為がダブリますね。
模範としたのでしょうか?
劉因って元に仕えるも一日で辞めて故郷に帰ったんですよね。確かに永楽帝の狂気の方が非難されてしかるべきだと思います。
永楽帝は方孝孺のことを許して徳を示すべきだったと個人的には思います。
またこうすれば少しは永楽帝に対する非難をかわす材料となったのに…
>>37
朱舜水は朱子学の理想を体現した存在として楠木正成を評価してますから、
仰る様に諸葛亮との朱子学ホットラインが形成され、
朱子学的評価の繋がりとして関係がありますね。
伯夷・叔斉の行為を彷彿させるから、多くの中から謝枋得が撰ばれたんだと思う。
本人が故事を知らないはずはないので、模範としたのは確実でしょう。
劉因もそうだけど、8人を選出した判断基準に、
キャラが立ってるという部分がないとは思えない。
書や詩の大家であるとか、そういった部分の方に、ウェイトが置かれてるけどね。
忠臣を捕らえた場合は、その高潔さを評価して○してやるのが礼儀かと。
顔真卿や文天祥の場合もそうだし。
禅の問答だかで、弟子と師匠が殴り合う話があるんだ。
生意気だからとか、気に食わないんじゃなくて、
相手の技量――悟りの度合いが深いことを評価して殴るんだよ。
それと似たようなもので、相手の忠義、人物を讃えるためにも、
永楽帝が方孝孺を評価したのなら、劇的な最後を演出してあげるのが覇者の勤めかと。
ただ、関係者、一族皆○しはやりすぎ。
方孝孺なんかは、明の永楽帝が甥の建文帝から位を奪った(靖難の変)為、太祖洪武帝・建文帝と二代に仕えた方孝孺は、永楽帝の招聘に応じず、かえって永楽帝の不義不忠を批判する始末。
怒った永楽帝は方孝孺の母方や妻方の親類縁者を含む九族を○すが、それでも従わなかった。
結局、方孝孺は磔にされ刀で両頬を耳まで裂かれたまま放置され、タヒぬまでの七日間罵り続けた。
孔明はこんなガチガチの原理主義者みたいな人と同列に論じられてるんだよね。
浅見絅斎の『靖献遺言』って勤皇の志士のバイブルなんでしょ?
この人の弟子にあたる三宅観瀾、朱舜水の弟子の安積澹泊らが
水戸学の基礎を築いたらしいですが、
浅見絅斎って朱舜水と共に水戸学の大本の大本ってことになりますね。
陶淵明・顔真卿・文天祥なんかも二心抱かなかった人物ですし、
生前の行動が大義名分論と王者の理論の両方に当て当てはまってますし。
故に諸葛亮と同列扱いしてるんでしようね。うーん趣味板だがアカデミックな議論も何げに好きだな。
現世利益に汲々とせず、己の思想に殉じてる。
方孝孺の遇し方を見ると、永楽帝の狂気の方が非難されてしかるべきだと思うが、如何。
>>39で名前が挙がってない謝枋得・劉因について。
謝枋得
文天祥と似た経歴をもち、元に仕えるを潔しとせず、その食すら食べずに餓タヒした。
劉因
元に使えるも職を辞し、隠遁生活を送った。
忠義の士の高潔さを尊重し、残された身内を手厚く保護すると。
こうすれば徳を示すことができますね。
自分は儒や朱子があまり好きではないので、ああ言う意見を述べました。
(孟子の方がまだ共感できるし)
個人的には為政者なら帝道をそれが無理ならせめて王道を歩むべきだと考えてます。
価値基準は外にあるものじゃなく、内に秘めたるものなんだ。
与えられた環境は、必ずしも良いとは限らない。
でも、その中で最大限の努力をするべきだ。
目先の利益や、一時的な快楽のために、立場を変えるのは卑しい。たんなる一個人の生き方、考え方の基準であれば、まったく問題がないのでは?
先に挙がっている人物も、賞賛されこそすれ、非難されることはないと思う。
彼ら至誠をつくし、強者といえども膝を屈しなかったことをもって、
名を知らしめているんだから。
現実に即した政治をすることでは?朱子学的に評価が高い諸葛亮は、政治家として無能だったわけじゃない。
その言行が朱子学のそれと合致したが、政策や施政は必ずしもそうじゃない。
朱子学とは関係ないけど、前秦の符堅の目指した国家ビジョンは、
後の唐朝のそれに近かったのでは、と考えている。
夢見がちの理想主義者であっても、現実から離れたり、無視したりしなければ、
実現は可能であり、帝道を歩もうが、王道を進もうが、失敗するのでは?
勝者の側は自分と戦ったことを赦して仕えさせようとするけど、勝者の赦す
という行為そのものが、当人たちの忠誠を否定することになるので。勝者の側もそれはわかっているから、本人は○すけど遺族を厚遇して決着
つけると。
ただ方孝儒の件はやりすぎでしょうね。やはり「簒奪」まで言われてしまうと
スルーできなくなってしまったんでしょうか。
孝明天皇の命により、京を守った松平容保と、
明治天皇を錦の御旗にした薩長では、
朱子学的にはどっちが正しいの?
どちらも正しいんじゃないのかな。
薩長の場合、最初、錦の御旗は下賜された訳じゃなかったんだけどね。勝手に偽ってたし。
あとで正式な錦の御旗は下賜されてるけど…
偽の錦の御旗の件はどう扱われるのだろう?
岩倉と大久保の陰謀なんだから。まぁ、朱子学って必ずしも矛盾なく論理的に現実を説明出来る思想じゃないからね。
朱子が仕えた宋と逆賊と批判する曹魏とたいした違いがあるわけじゃないから。
曹操・曹丕共に漢の臣なら、趙匡胤も後周の臣だし。
結局、湯武放伐を賞賛し易姓革命を容認するなら、天下を丸めたものが新たな天子ということになるし、これを否定するなら周以降の王朝はすべて簒奪となる。
「天は黙して語らず」だから、大義はどうとでも言えるからね。
まぁ、だからって何でもありって分けでもなくて、やっぱ「徳」てものによる縛りは帝王たる者にはついてくるけど。
やっぱりw
でも尊王、王政復古を達成する為には事後承諾も止むなしと考えてたんだろうか?
朱煕としては後周→宋の禅譲は戦乱期でしかも幼帝なので已むを得ず行った。
一方、後漢→曹魏は禅譲の体裁を整えても明らかに無理矢理、簒奪した。
と捉えてたのかも…
実際、そこら辺はどうなんだろ?
やはり大義はどうとでも言えるに行き着きのかな。あと水戸学では易姓革命を認めてないんだよね。
そうじゃないと天皇に不肖な者が現われたら、
将軍家とかがそれに取って代わってもいいことを容認してしまうし。
そもそも、明治維新自体、天皇が明確な意思に基づいて企画し薩長に命じたわけじゃないから。
>朱煕としては後周→宋の禅譲は戦乱期でしかも幼帝なので已むを得ず行った。
>一方、後漢→曹魏は禅譲の体裁を整えても明らかに無理矢理、簒奪した。
>と捉えてたのかも…
実際、そこら辺はどうなんだろ?
>やはり大義はどうとでも言えるに行き着きのかな。
朱子学的には、後漢→蜀漢→西晋と正統が受け継がれたとしてるけど、この論法が成り立つのは、曹魏が天下を統一出来なかったから。
曹魏が天下を統一してた場合、その正統性を否定してしまうと後の王朝に続かなくなっちゃうからね。
魏の曹氏は確かに酷い面があるが、晋の司馬氏も同様に酷いから。
確かに、水戸学は易姓革命を否定してるね。
だから、正確に朱子学の範疇に入るのかは微妙な感じがする。
神道と習合しちゃってるとこあるから、やっぱ「水戸学」と呼ぶしかなさそう。
前の方のレスに出て来た浅見絅斎の同門に佐藤直方がいるんだけど、この人は正統的儒者で天照大神の「天壌無窮の神勅」を無価値だとして、
「(天照大神が)子孫に不行義をするものあらば、けころ(蹴○)そうと仰せられたなれば、よいことぞ」
と言っている。
真に儒者なら徳を第一に考えるのが当然なんだけど、日本じゃこの直方の系統は結局メジャーにはならんかったんだよね。
有史以来、易姓革命や異民族支配を経験したことがなく、
万世一系の天皇が居る日本こそ本当の中華だ、みたいな事言っていたし。
水戸学的には日本も中国になるのかな?
本題の孔明だけれど、忠信として評価され、楠木正成と=されたのは講談だけ?
清=中国って発想がまず間違ってる。版図を今の中華人民共和国で発想してねーか?
清は、満州+モンゴル+トルキスタン+チベット+中国(中原)とかの連合王国。
朱子学や王学も批判するから、所謂中国って訳じゃねんだよな。
一番重要視したのは漢の文学だけどな。
字面では新田義貞=孔明だが、さらに楠木正成=孔明のメタファーが入ってるらしい
太平記は宋学的価値観も入ってるし、黄門様が伯夷伝を読んで感動したのも
実は史記じゃなくて太平記が引用する伯夷・叔斉の話を読んだからという説があるそうな
日本=中華論は山鹿素行の『中朝事実』にはじまるけど、水戸学でも同様だね。
まぁ、古代に天皇号を使いはじめた頃から、日本を中国とは別の天下という意識は芽生えてたけど、中国を夷狄視するのはこの頃からかな。
>本題の孔明だけれど、忠信として評価され、楠木正成と=されたのは講談だけ?
太平記読みや講談での正成は忠臣のイメージももちろんあるけど、希代の軍略家としてのイメージが強かったかも。
由井正雪は正成の子孫と称する軍学者に学び、正成の軍略を講じて多数の門人をかかえてたから。
孔明も元曲の『三国志平話』までは、忠臣というより神算鬼謀の道士のような感じで、いかにも民衆受けするヒーロー像だった。
演義としてまとめられる過程で、仏教的な因果応報や輪廻転生、荒唐無稽な道術ぽいのとかはかなり削られて、朱子学的な倫理観を前面に出して再構成された感じかな。
このおかげで、士大夫が読むに堪える物になった。
正成も似たような所があり、朱舜水が正成を忠臣として再評価してからは、日本の知識人(=儒者)の間では、楠公がブームになってる。
ほとんどの人がスレタイ通り、
マジメに朱子学の論点から語ってるのがそんなに可笑しいのか?
ん、つーかね。孔明の話が殆ど出てないのが問題なのだよ。
そこで笑ったわけ。
だからスレ立てた奴がア○なだけでネタスレなんかと思って覗き見てるから、
そんなこと言ってるだけにしか見えないけどなw
>>58氏も言ってるが朱子学は素より水戸学がどういうものなのかと意見を絡めつつ、
諸葛亮が朱子学に置いてどう評価されてるかを述べてるつもりなのだし、
問題あるとは思えない。
またなぜ君が笑うのか理解できないな…
軍才や人物眼云々のスレや議論は三戦の時からで飽きるほどやったんだし、
個人的にはアカデミックな論議を楽しんでる訳だ。
冷やかし又はこれと言った主張がないなら黙っててくれないか。>>60
だよな。前にもなんか勘違いしてた奴がいたけど、それと同類かと思われ。
朱子学とは何か?それがどう受容されてきたか?
そこがハッキリしないと、諸葛亮の評価に関して朱子学が、
どのように関与したか分からない。それともスレ違いの話に終始してれば満足なのか?
読み飛ばしてるだけじゃね?
「私の勤務校は朱子学の学校なので孔明をけなすと立場が危ない」
みたいな話をして受けたらしい
あの頃は朱子学に王朝自体が、否定的。満州も特別地区。
礼学とかの研究に偏るし、後金はハーンから来る皇帝号だから
やっぱり、朱子学を否定したかったんですかね?清成立時は、中華(中原)皇帝の皇帝号も持っていますが…
ハーン号の方が上なのでしょうか?
この当時の清の諸葛亮の評価が知りたいです
…先生…
清代後期には考証学に飽きて朱子学に回帰する動き(?)もあったらしいから
清朝が一概に朱子学を否定したかったとも言い切れないのでは?その頃の孔明の評価はちゃんと調べんと分からんけど、
演義が発禁もされず普通に読まれてた事や
漢民族懐柔のためとはいえ、関帝信仰を清朝が公認してた事などからすれば
孔明ら蜀将は少なくとも邪険に扱われる事は無かったんじゃないですか
ただ、彼の行った北伐が、魏を北方民族に変換されたら困る。
反清復明運動に利用されない限り、諸葛亮をわざわざ否定して、波風はたてたくない。こんな感じ。
むしろ過剰評価されたのは李網じゃね?
頼山陽がなんか出してたでしょ。
天子となれ」と言われていたにもかかわらず、
とうとう皇位を簒奪しなかった。
その忠義ぶりが、諸葛亮を益々
英雄たらしめているんだろうね。
論語・孟子等とは比べ物にならん。
一番好きだけど。
やっぱり学者や政治家として生きてほしかったなぁ。
博学だし、生活も質素だしね。
肉体労働の忌避や金銭を賤しむ考えや選民思想とか共通するところがあるし
実際宋の都、開封には唐代から多くのユダヤ教徒がいたし
朱熹もこれに影響を受けて現在の朱子学を体系化したのではないのだろうか
そもそも秦の始皇帝はアラビヤ出の皇帝
漢の劉家もアラブの刺客アラビヤンは貧者向けに世界三大宗教を樹立した
貧者とは、アラビヤンの支配下にない自然の状態で生きていた場合に
自然界から本来得られるはずの自然の恵みの量、
それ以下の恵みしか得られずにアラビヤンの支配の元、生かされている奉公人
その差分が富めるアラビヤンに流れる
アラビアじゃなくて中央アジアだろ
当時はグレコ・バクトリア地方
引用元: https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/chinahero/1190128235/
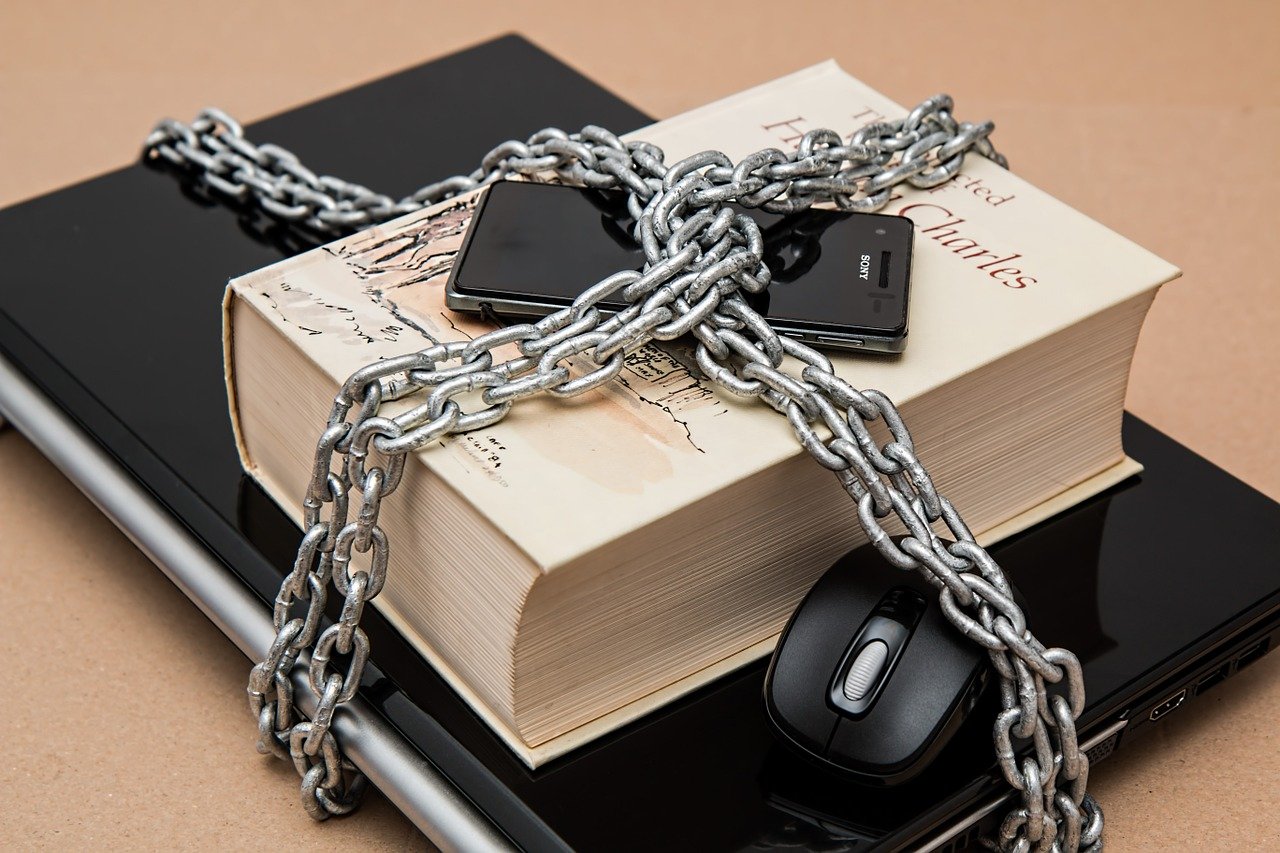
コメント
コメント一覧 (1件)
朱子学は後醍醐天皇を生んでるし、日本にとって完全に害毒